脊髄損傷の方が多くなる褥瘡について、改善するためのポイントを紹介していきます。褥瘡は少し気を抜くとすぐにできてしまいますが、一旦できてしまうと治るのにとても時間がかかります。
その褥瘡を治すためのポイントについて、紹介していきます。
左お尻坐骨の上にできた褥瘡

私は脊髄損傷になって、すぐ入院したリハビリ病院で褥瘡ができてしまいました。まだ褥瘡ができるという概念がほとんど頭に入っておらず、一日中プッシュアップもせずに座り続けるということをしてしまいました。
そのため左のお尻の坐骨の上に褥瘡ができ、出血するということが起きてしまいました。
その後も今おこなっているようなケアや、プッシュアップなどはほとんどしなかったので、褥瘡は悪化していきました。10cm近いポケット(穴)ができ、専門の病院へ入院しました。
褥瘡改善のポイント
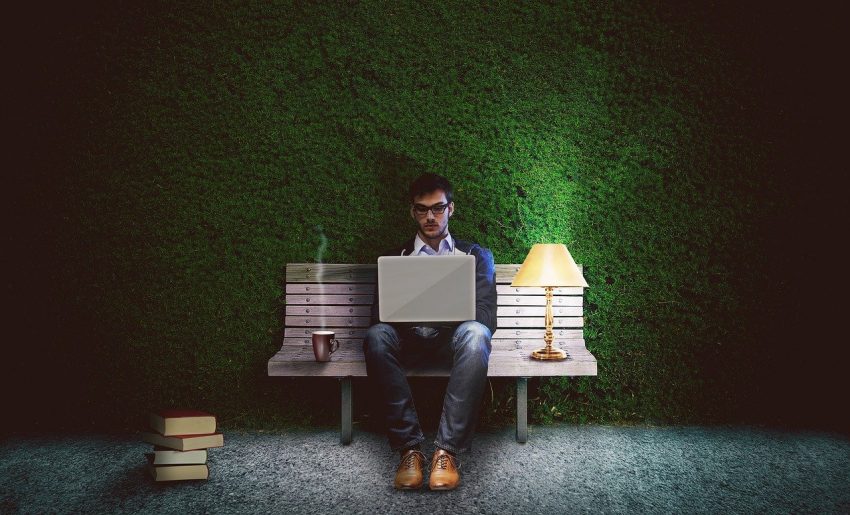
私はウォックナースの看護師さん(褥瘡専門の看護師さん)ももう治らないのではないか、と言っていた褥瘡は5年かかりましたが治りました。
その間手術をしたりもしましたが、その過程で褥瘡が治るのに役に立ったことを伝えてきたと思います。
褥瘡のケアは、自分でできることとケアしてもらうことがあります。褥瘡に対してできることは自分でできることと、看護師さんなどにケアしてもらうことに分かれます。
まず先に一般的な褥瘡に関する措置についてお伝えしていきます。褥瘡ができたら、誰でも実施していると思われる褥瘡の処置です。
私の場合には、週に2回看護師さんが処置して、その他の日は両親にやってもらっていました。ポケットがあった時は、ポケットの中に薬を注入し、そして綺麗に洗うということをしてもらっていました。
褥瘡の穴が閉じ浸出液がなくなるまでは、およそ5年間、褥瘡を毎日洗い続けました。
自分でできる褥瘡のケア

自分でできる褥瘡のケアは効果があるものとして、2つあります。
一つは除圧です。
車椅子に乗っている時もベッドに寝ている時も除圧しました。夜の間は7時間ほど寝たままでしたが、特に悪化することもなく治っていきました。
特に車椅子に乗っている間は、頻繁に除圧(プッシュアップ)をしています。
プッシュアップはリハビリ病院で最低1分はやってほしいと言われてたのですが、筋肉痛でそこまでは出来ていません。車椅子に乗り移った最初に1分して、それ以降は7分から10分に1回ぐらい25秒から30秒程度除圧しています。
褥瘡は治った今でも防止のために、除圧(プッシュアップ)は続けています。褥瘡が治るのに5年もかかったので、もう二度と褥瘡を作りたくないという思いでプッシュアップはしています。
7分から10分程度に一回25秒か30秒するだけで褥瘡は治ってきました。
そして、自分でできるケアはもう一つあります。
HMB サプリメントを飲む

褥瘡のケアには、タンパク質を大量に摂取することが必要とインターネットで勉強しました。そしてたまたま、たんぱく質が分解されたHMBサプリメントを筋肉増強のために飲んでいました。
最終的に治らないと思われてた褥瘡が治ったのは、このHMBサプリメントを飲んだためだと思います。HMBサプリメント飲んでから、急激に褥瘡が小さくなっていきました。
HMBサプリメントは高いものでは1万円ぐらいするものもありますが、私は1か月分1200円から1500円ぐらいの安いものを飲んでいて、効果がありました。
まとめ

その他にもう一つ劇的に褥瘡が小さくなったものがあります。
それは褥瘡のために入院し、陰圧閉鎖療法と言う施術を施術しことです。(手術ではありません。)陰圧閉鎖療法とは褥瘡に対し、吸引し浸出液を吸収し圧力の力で皮膚を引き上げるというものです。
これを保険適用がある1ヶ月の間毎日続けていました。陰圧閉鎖療法の効果はかなりあり、半分まで褥瘡小さくなりました。
結果的に今思い返せば、褥瘡が治るのに必要だったことは、以下のことです。
それから、毎日夜にヒーリングが得意な方にヒーリングもしてもらっていました。
褥瘡専門の看護師さんは治らないだろうと思っていた褥瘡が、治ったので、この方法でどんな褥瘡も治るのではないかと思います。私の場合は、座骨の上にある褥瘡だったので、座るとすぐに悪化してしまう場所だったのが治りにくかった原因です。
まだ陰圧閉鎖療法を受けたことがない方は、ぜひ病院を探して受けてみてください。私は、4つくらいの病院に問い合わせたところ、二つの病院は実施していました。
褥瘡に関する情報が、お役に立てたら嬉しいです。
褥瘡については、こちらの記事も参考にして下さい。
障害を持っていても障害を理解し働けるようになったら嬉しいですよね。
障害別の就労移行支援のサービスがあります。
障害理解・対処スキル習得、ビジネススキル習得、実践トレーニングをしてくれるサービスがあります。そして、身体障害によりなかなか外出できない方が ITやWeb サービスのスキルを身につけることも可能です。
さらに就職活動をサポート、就労後もサポートしてくれます。
障害別に特化したスキルを身に付け、就職のサポートが受けられるのです。
障害を持っていても、働きたいと考えている人をサポートしてくれます。




コメント